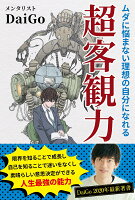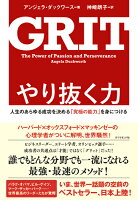Contents
【保存版】目標が見つからない人必見!コーチングの4つのレベルから考える人生の最適化方法
どうも、効率人生研究家のSHOです。
『人生の最適化』をテーマに、効率よく目標を達成するための考え方や行動戦略を発信しています。
YouTube、Instagram、TikTokを毎日更新中!
目標はYouTubeチャンネル登録者1万人を目指しています!
ぜひフォローしてもらえると嬉しいです!
さて、今回のテーマは「目標の見つけ方」。
「自分は何を目指すべきか分からない…」そんな悩みを抱えていませんか?
目標がないとモチベーションが湧かず、行動も中途半端になりがちです。
そこで今回は心理学的なアプローチを使って、目標を見つけるための5つの方法を解説します。
この記事を読めば、「本当に自分がやりたいことは何か?」が明確になり、スッキリした気持ちで次の一歩を踏み出せるはずです。
それでは早速、目標が見つからない原因から一緒に考えていきましょう!
なぜ、目標が見つからないのか?
目標が見つからない理由は、実は意外とシンプルです。
「自分の現在地が曖昧で、未来のゴールがぼやけているから」。
心理学的にも人は「不確実性」に直面すると、行動を先延ばしにする傾向があります。
要するに、「どこに向かうべきか分からないから、動き出せない」という状態に陥っているのです。
では、なぜ現在地と未来のゴールが曖昧になるのでしょうか?
その背景には、脳の仕組みも関係しています。
脳は「現状維持」を好むように設計されています。
これを「現状維持バイアス」と言います。
新しい目標を設定すると、脳は「リスクがある」と判断し、あえて動かないようにさせてしまうのです。
さらに、過去の失敗体験がブレーキになることもあります。
たとえば、「前に目標を立てたけど、うまくいかなかった…」という経験があると、無意識に「どうせ今回も失敗する」と考えてしまいます。
これが心理学で言う「学習性無力感」です。
この状態になると、「やっても無駄だ」と感じて行動が止まってしまいます。
コーチングの視点から見ると、目標が見つからないのは、「視野が狭くなっている状態」と考えられます。
普段の仕事や生活に追われていると、「目の前のタスクをこなすこと」に意識が集中しがちです。
その結果、人生全体のビジョンや中長期のキャリアについて考える時間が取れず、目標を見失ってしまうのです。
効率人生研究家の観点から言えば、「現状の把握が甘い」のも原因です。
目標を見つけるためには、まず「自分が今どの位置にいるのか」を明確にしなければいけません。
しかし、忙しさや日常のルーティンに追われていると、改めて自分のスキルや価値観、興味のあることを振り返る機会が減ります。
その結果、「自分が何をしたいのか分からない」と感じてしまうのです。
要するに、目標が見つからない原因は、脳科学的なバイアス、過去の失敗体験、情報不足、そして自己認識の甘さに集約されます。
これらを解決するためには、まず「自分の現在地」と「目指したい未来」を明確にすることが重要です。
そして、これをサポートしてくれるのが「コーチングの4つのレベル」の考え方です。
次の章で、具体的な目標の見つけ方を解説していきます。
目標を見つけるための5つの方法【コーチングの4つのレベルで考える】
1. 案件レベルの目標を明確にする
まずは、目の前の「小さな案件」から目標を考えてみましょう。
案件レベルの目標とは、日々のタスクや仕事に関する短期的な目標のことです。
この段階では、あまりにも大きな目標を立てる必要はありません。
人間の脳は大きな不確実性に対して不安を感じやすいようにできています。
そのため、「1年後にどうなりたいか?」といった抽象的な問いよりも、「今週中に終わらせるタスクは何か?」という具体的な問いの方が行動に結びつきやすいのです。
目標を明確にするポイントは、「次に何をすればいいかが一瞬でわかること」です。
「明日までに○○を提出する」「午後2時までに会議資料を仕上げる」といった具体的なアクションを設定しましょう。
目標が具体的であればあるほど、脳はその行動に向けて自然に動き始めます。
これは、脳の「RAS(網様体賦活系)」の働きによるものです。
RASは重要な情報を優先的にキャッチするフィルターの役割を果たしており、明確な目標を設定することでその目標に関連する情報が自然と目に入るようになります。
また、心理学的にも、「小さな成功体験」を積み重ねることが、自己効力感(自分はやればできるという感覚)を高める鍵だとされています。
「案件レベル」の目標を1つ1つクリアするたびに、脳は「自分はやればできる!」と感じるようになり、モチベーションが自然に高まります。
これが「成功循環モデル」の考え方です。
コーチングの世界でも、「最初の一歩を小さくする」という考えがよく用いられます。
あまりにも高い目標を設定すると、脳はそれを「無理なこと」として認識してしまいますが、逆に「今すぐできる一歩」なら取り組みやすいのです。
具体的には、「5分だけ資料を作る」「3つのアイデアをメモに書く」といった行動が該当します。
これが「スモールステップの法則」であり、行動が動機を生むというのもこの考えに基づいています。
案件レベルの目標は、あくまで短期的なものです。
しかし、この短期的な目標が達成されるたびに、自己効力感が高まり、自然と次の大きな目標にも挑戦したくなるという好循環が生まれます。
まずは「今何ができるか?」を考え、行動し、1つの目標を達成してみましょう。
そうすることで、自然と次の目標も見えてくるはずです。
2. 現職レベルの目標を見つける
現職レベルの目標を考えるとき、ポイントは「今の仕事をどう意味づけするか?」にあります。
目の前の仕事をただのタスクの集合体と捉えるか、自分のキャリアの土台作りと捉えるかで行動やモチベーションは大きく変わります。
心理学では「モチベーションの源泉」は大きく2つに分けられます。
1つは「外発的動機付け」で、これは上司からの評価や給与、昇進などの外的な報酬がモチベーションの源になるもの。
もう1つは「内発的動機付け」で、自分の成長実感や好奇心、達成感がモチベーションの源になります。
現職の目標を見つけるためには、外発的動機と内発的動機の両方を活用するのが効果的です。
例えば、上司からの評価を目標にするのも大事ですが、それだけだと長続きしません。
そこで、「このスキルを習得すれば、次のキャリアでも生きる」といった“自分の成長”という内発的な目標も同時に設定するのがポイントです。
脳科学の観点では、人間の脳は「小さな成功」を積み重ねるとドーパミンが分泌され、次の行動が取りやすくなる性質があります。
したがって、いきなり大きな目標を立てるのではなく、「1週間以内に報告書を完成させる」「3日以内に新しい提案を1つ作る」といった小さな目標を設定するのが効果的です。
これにより、達成感を味わいやすくなり、次の行動が自動的に起こりやすくなります。
さらに、コーチングの考え方では、「なぜその目標を達成したいのか?」を深掘りするのが鉄則です。
人は「やりたい理由」が明確になると、行動のエネルギーが自然と湧いてきます。
たとえば、単なる「資格を取る」ではなく、「この資格を取れば、将来の選択肢が広がる」という未来志向の理由をセットにするだけで、行動の継続率が高まります。
効率人生の観点から言えば、目標は常に“最小の努力で最大の効果が得られるもの”を目指すのがポイントです。
「この作業は本当に自分がやるべきか?」と自問し、やるべきではないタスクを捨てる勇気も必要です。
限られた時間の中で最大限の成果を出すためには、目標の優先順位をつけ、効率的な働き方を模索する必要があります。
現職レベルの目標を見つける際は、外発的な報酬と内発的な報酬をバランスよく取り入れ、小さな成功体験を積み重ね、なぜその目標を達成したいのかを深掘りしつつ効率よく進めるための工夫をすることが大切です。
これを意識するだけで、現職での成果が確実に変わってきます。
3. キャリアレベルの目標を見つける
3つ目は、キャリアの観点から目標を考える方法です。
「あなたは5年後、どんなキャリアを築いていたいか?」この問いを自分に投げかけてみましょう。
キャリア目標は、「大きなビジョン」を描く感覚が重要です。
今の現職だけにとらわれず、「自分の価値をどこで活かすか?」を考えましょう。
脳科学の観点では、人間の脳は「予測可能な未来」を好む性質があります。
5年後、10年後の未来を想像するだけでも、脳はその未来を実現しようとする回路を自然に作り出します。
これが「メタ認知」と呼ばれるもので、自分の将来を客観的に俯瞰できる力につながります。
未来の自分を想像するときは、なるべく「細かいシチュエーション」をイメージしてください。
例えば、「スーツを着て大勢の前でプレゼンをしている自分」や「ノマドワーカーとしてカフェでPCを打つ自分」など、具体的な場面が脳の活性化を促します。
心理学では、「成長欲求」が人の行動の源になると考えられています。
仕事をただの「義務」と捉えるとモチベーションが続きませんが、「自分が成長している」という感覚が得られるとやりがいを感じ、自己実現の欲求が刺激されます。
キャリア目標を立てる際は、「自分がどう成長していたいか?」を明確にすることがカギです。
また、コーチングの手法では、「現在の状態」と「理想の未来」のギャップを明確にすることが推奨されています。
現状のスキル、強み、弱みを棚卸しし、未来のゴールと照らし合わせることで、「今、何をするべきか」が明確になります。
このギャップ分析の結果をもとに、毎月の目標、年間の目標を具体的な行動プランに落とし込むことが効果的です。
たとえば、次のようなキャリア目標が考えられます。
- 2年後にチームリーダーに昇進する
- 3年以内に社内の異動制度を利用して、マーケティング部門へ移る
- 5年後には独立してフリーランスのコンサルタントになる
これらの目標を実現するためには、日々の「小さな行動」の積み重ねが必要です。
脳は「すぐに達成できる報酬」に強く反応するため、1日の中で達成感を味わえる「小さなゴール」を積み重ねていくのがポイントです。
「今日中に1冊の本を10ページ読む」や「上司に1つの提案をする」といった些細な行動が、最終的なキャリアの目標に向かう力を生み出します。
4. ライフレベルの目標を見つける
人生全体の目標を考えるとき、最も重要なのは「本当に自分はどう生きたいのか?」という問いに向き合うことです。
仕事やキャリアの延長線上にある目標ではなく、人生の根本に関わる目標を見つけるフェーズです。こ
のプロセスは多くの人が避けがちですが、ここをクリアにすることで人生のあらゆる選択がスムーズになります。
脳科学の観点では、「未来の自分を具体的にイメージすること」が目標達成のカギとされています。
人の脳は、具体的なイメージがある方が行動しやすくなるため、将来の自分の姿を詳細に想像することがポイントです。
例えば「50歳になったときにどうなっていたいか?」「周りからどんな人だと思われたいか?」を考えるだけで、日々の行動が変わります。
これは、"未来予測の脳内シミュレーション"と呼ばれ、モチベーションを高める効果があると言われています。
また、心理学の「モチベーション理論」では、目標は内発的動機付けが強いほど達成しやすいとされています。
つまり「誰かのため」や「社会的な評価」のためではなく、純粋に「自分がやりたいからやる」目標の方が、持続性が高いのです。
「これをやりたい」と思えることを見つけるためには、過去の成功体験や、自分が夢中になれた瞬間を思い出してみるのが効果的です。
具体的な方法としては、「自分年表」を作るのがおすすめです。
これまでの人生の出来事をリストアップし、その中から自分が「達成感を感じた出来事」や「心から楽しかった経験」をピックアップしていきます。
そこから共通点を見つけると、あなたが本当に大切にしている価値観や、心が動かされる分野が浮かび上がります。
この作業は、自己分析のための手法として多くのコーチングでも使われており、人生の軸を見つけるうえで非常に有効です。
結局のところ、ライフレベルの目標とは、単なる数値目標ではなく、「どういう生き方をしたいか」という価値観の明確化です。
この価値観が明確になると、日常の意思決定がスムーズになり、後悔のない選択ができるようになります。
日々の迷いを減らし、後悔しない人生を送るためにも、ぜひ自分の価値観を明らかにしてみてください。
5. 現状把握とリソースの抽出(過去・現在・未来の視点)
目標を見つけるためには、まず「自分が持っているリソース」を明確にすることが大切です。
リソースとは、簡単に言えば「自分が使える資源」のこと。
過去の経験、現在のスキル、将来の可能性など、すべてがリソースに該当します。
心理学の観点からも、「自己効力感(自分はできるという感覚)」を高めるためには、「自分が何を持っているのかを把握する」ことが効果的だと言われています。
これにより、自信がつき、次の一歩を踏み出しやすくなります。
具体的なやり方としては、「過去」「現在」「未来」の3つの視点からリソースを洗い出す方法が有効です。
- 【過去】…これまでに経験した成功体験、乗り越えた課題、身につけたスキル
- 【現在】…今の自分が使えるスキル、人脈、時間の使い方、習慣
- 【未来】…これから学びたいスキル、得たい経験、実現したいこと
この3つの視点からリソースを整理するだけでも、「意外と自分はたくさんのものを持っているんだな」と気づけるはずです。
さらに、効率的に目標を達成するためには、「モデリング」の考え方も取り入れるのがポイントです。
モデリングとは、簡単に言えば「成功者のやり方を真似る」ことです。
脳科学的にも、人は模倣を通じて学ぶ力を持っているため、周囲の成功者やロールモデルから学ぶのは非常に有効な手法です。
例えば、「この人の働き方が理想だな」と思う人がいれば、その人のスキルセットや考え方、時間の使い方を研究してみてください。
直接その人に話を聞けるなら最高ですが、SNSや書籍からでも十分にモデリングは可能です。
成功者の思考や行動を自分のリソースに変えることができます。
リソースを見つける過程で、過去の自分を振り返るのは、自己肯定感を高める効果もあります。
過去に自分がやり遂げたことや、難しい状況を乗り越えた経験を思い出すだけでも、「あの時できたんだから、今もできるはずだ」という感覚が生まれます。
これらのリソースを把握しておくと、「何を使えば次の一歩を踏み出せるか」が具体的になります。
現状把握の段階で自分の持つリソースを明確にしておけば、目標の設定もスムーズになりますし、行動計画も立てやすくなります。
最後に大切なことは、「リソースは今からでも増やせる」という考え方です。
新しいスキルを身につけるのも、信頼できる人脈を築くのも、すべてリソースを増やす行動です。
モデリングを活用し、過去・現在・未来の視点でリソースを見つけることで、あなたの行動は大きく変わっていくはずです。
まとめ:目標を見つけて人生を最適化しよう!
ここまで、目標の見つけ方について「コーチングの4つのレベル」を使った方法を解説してきました。
目の前のタスクから、現職、キャリア、人生全体に至るまで、異なる視点で目標を考えることで、「自分は何を目指すべきか?」がはっきりしてくるはずです。
特に、過去・現在・未来の視点を使ったリソースの抽出は、目標を考える上で非常に効果的な手法です。
これまでの経験やスキル、現在の状況、これからの未来を見据えることで、あなたの「強み」や「可能性」がクリアに見えてきます。
目標が見つからない理由は、「自分の現在地が不明瞭」だったり、「ゴールがぼんやりしている」ことが多いです。
これを解消するためには、まずは小さな目標から取り組むのがおすすめです。
日々のタスクや案件レベルの目標をクリアすることで、次第に自信がつき、より大きな目標も見えてきます。
また、人生全体の目標(ライフレベルの目標)については、すぐに答えが出なくても大丈夫です。
大事なのは、「自分はどういう人生を送りたいか?」を考え続けること。
キャリアの転換期や環境の変化に応じて目標は変わるものなので、柔軟に見直していきましょう。
目標が明確になると、行動も変わります。
目指す場所が決まれば、必要な行動が分かり、行動すれば結果が変わります。
最初の一歩を踏み出すために、まずは「自分の現状を把握する」ところから始めてみてください。
もし「もっと詳しく知りたい」「具体的なやり方が知りたい」と思った方は、ぜひYouTubeチャンネルもチェックしてみてください!
動画では、目標設定や行動のコツについて、より具体的なアドバイスをお届けしています。
人生の最適化は、1日や2日で終わるものではありませんが、「行動の質を変える」ことで、確実に未来は変わります。
ぜひ今回の内容をヒントにして、あなたの人生に新たな目標を見つけてみてください!