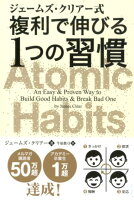Contents
【人生をものにする!】主体的に人生を切り開くための5つの秘訣
どうも、効率人生研究家のSHOです!
『人生の最適化』をテーマに、効率的に目標を達成するための考え方や行動戦略を発信しています。
毎日SNSを更新中!
YouTube・Instagram・TikTok で最新の情報をお届けしています。
目標は「YouTube登録者1万人」!
応援してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです!
さて、今回のテーマは「自分の人生をものにするための主体的な切り開き方」です。
あなたは、自分の人生を「自分の手で動かしている」と言い切れますか?
気づけば他人の期待に応える日々、職場のルールに従うだけの毎日…。
「これ、本当に自分の人生だっけ?」と思う瞬間があるかもしれません。
でも大丈夫です。
主体的に人生を動かす秘訣は、心理学と脳科学の観点から明確になっています。
この記事では、心理学・脳科学の理論をもとに、実行しやすいアクションを厳選してお届けします。
この記事を読んだ後には、「あ、これならできるかも!」と感じるはずです。
それでは行きましょう!
なぜ、主体的に生きるのは難しいのか?
この考え方は、『7つの習慣』(著:スティーブン・R・コヴィー)と、『嫌われる勇気』(著:岸見一郎・古賀史健)からの抜粋です。
この2冊は、なぜ人が「主体的に生きることが難しいのか」を明確に説明している代表的な本です。
まず、『7つの習慣』では、「主体性を持つことは、人生を変える最初の習慣である」と述べられています。
しかし、なぜ多くの人が主体的に生きられないのでしょうか?
その理由は、「刺激と反応の間にある選択の余地を見失っているから」だとされています。
多くの人は、環境や他人の行動に影響されて、自分の行動を「反射的に決めている」状態にあります。
たとえば、上司に怒られたらイライラし友人に否定されたら落ち込む。
これは、「自分の感情は他人がコントロールしている」という思い込みによるものです。
しかし、スティーブン・R・コヴィーは、「刺激と反応の間には選択の余地がある」と指摘します。
上司の言葉がどうであれ、感情や行動を選ぶのは自分自身です。
主体的に生きるためには、環境や他人に支配されるのではなく、「自分がどう反応するかを選ぶ力」を持つことが必要です。
次に、『嫌われる勇気』では、なぜ主体的に生きられないのかを、「他者からの承認欲求に縛られているから」だと解説しています。
アドラー心理学では人が他人の期待に応えようとする「承認欲求」を手放さなければ、真の自由(主体性)を得ることはできないと説かれています。
人は無意識のうちに「他人にどう思われるか」を気にして行動してしまい、結果的に「本当にやりたいこと」ではなく、「他人の期待に沿った行動」をとってしまうのです。
アドラーは他者の承認を求めるのではなく、「自分のために行動する勇気」を持つことが必要だと主張しています。
これがいわゆる「課題の分離」という考え方です。
たとえば、職場での評価や人間関係の問題は他人の「課題」であり、自分の課題ではないと考えます。
これにより、「他人の課題に振り回されるのではなく、自分の課題に集中する」ことができ、主体的な行動が生まれます。
まとめると、『7つの習慣』の「刺激と反応の間にある選択の余地を見つける」考え方と、『嫌われる勇気』の「承認欲求を手放し、課題の分離を行う」考え方を組み合わせれば、「環境や他人の評価に左右されず、自分の意志で行動を選び取る主体性」を手に入れられます。
自分の人生を主体的に切り開くための5つの秘訣
1. 「行動の引き金」をセットする
この考え方は、ジェームズ・クリアの名著『アトミック・ハビット』からの抜粋です。
行動の引き金をセットするとは、「既存の行動に新しい行動を結びつけることで、新しい習慣を作る手法」のことです。
これを「ハビット・スタッキング(習慣の積み重ね)」と呼びます。
たとえば、「朝のコーヒーを飲んだ後に5分だけ読書をする」「歯を磨いた後に1回だけスクワットをする」といった方法が典型的な例です。
ポイントはすでに無意識に行っている行動(コーヒーを飲む、歯を磨く)を「トリガー(引き金)」として活用することです。
これがなぜ主体的な行動を生み出すのか?脳科学の視点から解説すると、脳は「現状維持を好む」特性を持つため、まったく新しい行動を単独で始めようとすると、大きなエネルギーを必要とします。
新しい行動を始めるたびに「意志力」が消費され、挫折しやすくなるのはこのためです。
しかし、『アトミック・ハビット』で解説されている「ハビット・スタッキング」は、すでに脳にインプットされている「既存の行動」に新しい行動をくっつけるだけなので、脳の抵抗を受けずに、自然な流れで新しい行動が追加されるのです。
たとえば、「歯磨き後にスクワットを1回する」という習慣を作る場合、すでに定着している「歯磨き」の後に自然な流れで体を動かすだけで済みます。
これにより、「あれをやらなきゃ…」という強い意志力を使う必要がなくなり、主体的な行動が取りやすくなります。
また、心理学の観点からも行動の引き金を使う手法は有効です。
人間の行動の約9割は「無意識の習慣」によって支配されています。
これを裏付けるのが、「デュアルプロセス理論」です。
この理論によれば、私たちの脳は「自動的なシステム1」と「意識的なシステム2」で動いています。
普段の習慣はシステム1(自動運転モード)で行われているため、意識的に新しい行動を始めるのは難しいのです。
しかし、「行動の引き金」を活用すれば、システム1に直接アクセスして、無意識に新しい行動を始めることが可能になります。
これにより、自分の意志で行動をコントロールしている感覚が得られ、「主体性」が生まれるのです。
つまり、行動の引き金をセットするというのは、「自分の行動の流れを自分でデザインすること」です。
これこそが主体的な生き方を実現するための第一歩です。
ぜひ、あなたの毎日の習慣の中から「引き金」となる行動を見つけ、その後に続けたい行動をくっつけてみてください。
2. 「小さな行動」を続ける
この考え方は、ジェームズ・クリアの『アトミック・ハビット』と、BJ・フォッグの『Tiny Habits(小さな習慣)』からの抜粋です。
両書籍に共通するのは、「小さな行動を積み重ねることが、自己変革の最も効果的な方法である」という考え方です。
なぜ「小さな行動」が重要なのか?
それは、人間の脳が「変化を嫌う性質」を持っているからです。
脳科学では、脳はできるだけ省エネルギーで動こうとするため、大きな目標や負担のかかる変化は拒絶しようとする働きがあります。
これが「ダイエットが続かない」「勉強を三日坊主で終わらせてしまう」といった現象の原因です。
しかし、小さな行動は脳の抵抗をほとんど受けません。
たとえば、「腕立て伏せを1回だけやる」「本を1ページだけ読む」といった行動なら面倒だと感じることはありません。
この考え方は、BJ・フォッグが提唱する「Tiny Habits(小さな習慣)」の核となる考え方です。
BJ・フォッグは、行動を定着させるための3つの原則を提示しています。
それは、「簡単にする」「小さく始める」「トリガーを活用する」の3つです。
特に「小さく始める」ことが重要で、彼は「1回のスクワットでも行動は始まる」と強調しています。
最初の一歩が小さければ小さいほど、脳の「面倒だな」という抵抗を受けにくくなります。
では、小さな行動が主体性につながる理由は何でしょうか?
これは、「自己効力感(self-efficacy)」の向上に関係しています。
自己効力感とは、「自分はやればできる」という感覚のことです。
人は成功体験を積むことで自己効力感が高まり、次の挑戦への自信が生まれます。
たとえば、1日30分の筋トレを始めようとすると、途中で挫折する可能性が高いですが、「腕立て1回だけなら」と決めた場合、99%の人が成功できます。
これを繰り返すと、「自分はやればできる」という感覚が生まれ、行動が自発的に行えるようになります。
主体的な行動は、この「自己効力感の積み重ね」によって生まれます。
さらに、『アトミック・ハビット』では、クリアは「1%の改善の積み重ねが人生を大きく変える」と述べています。
毎日わずか1%の成長を続ければ、1年後には約37倍の成長を遂げるという理論です。
これがいわゆる「コンパウンド効果(複利効果)」です。
最初は小さな変化でも、時間が経つにつれて大きな変化になるため、主体的な行動がより強力になります。
まとめると、「小さな行動を続ける」ことは、脳の抵抗を受けにくいだけでなく、自己効力感を高め、主体的な行動を生み出す効果的な方法です。
大きな目標を掲げるのではなく、まずは「たった1回の行動」を決めて、続けてみてください。
それが、主体的な人生を切り開く第一歩になります。
3. 「自分の価値観」を知る
この考え方は、スティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』からの抜粋です。
『7つの習慣』の中で、最も有名な第2の習慣が「終わりを思い描いてから始める」です。
この考え方の本質は、「自分の価値観を明確にし、人生のゴールを自分の意思で決める」ことにあります。
なぜ価値観を知る必要があるのでしょうか?
その理由は、「価値観が主体性の根幹を支えているから」です。
もし、自分の価値観が明確でなければ、周囲の意見に流されやすくなります。
たとえば、親の期待や社会の常識に従って職業を選んでしまうと、後から「これ、本当に自分がやりたかったこと?」と疑問を感じることが多いのです。
スティーブン・R・コヴィーは、人生を動かす2つの軸として「緊急性」と「重要性」を挙げ、価値観に沿った行動は「重要だが緊急ではないこと」に集中すべきだと説きました。
価値観が明確な人は重要な行動に集中できるため、他人の意見に振り回されず主体的な行動が取れるのです。
では、どうすれば自分の価値観を明確にできるのでしょうか?
『7つの習慣』では、次の質問が推奨されています。
- あなたが一番大切にしているものは何ですか?
- あなたの人生の最終ゴールは何ですか?
- 何をしているときが一番幸せだと感じますか?
- あなたが理想の自分に近づくために必要なことは何ですか?
この質問に答えることで、あなたの中に眠る価値観が明確になります。
また、心理学の観点からも、「自己決定理論(SDT:Self-Determination Theory)」によって、価値観を基盤にした行動が最も持続しやすいことが分かっています。
SDTによると、人間が最も主体的に行動できるのは、「自律性、関係性、有能感」の3つの欲求が満たされたときです。
価値観を明確にすることで、「自分で選んでいる感覚」が強まるため、主体的な行動が自然に生まれるのです。
たとえば、もしあなたの価値観が「自由」だと気づいたとしたら、転職の際には「自由に働ける環境か?」を基準に選べるようになります。
これにより、他人の評価ではなく「自分の基準」で物事を判断できるようになります。
この「自分の基準」が主体性の土台となるのです。
まとめると、『7つの習慣』の考え方や、自己決定理論を取り入れた「価値観の明確化」は、主体的な行動を生み出す重要な要素です。
価値観が定まると、意思決定がブレなくなり、他人に流されることが減ります。
まずは、自分の価値観を書き出してみることから始めてみてください。
あなたの価値観が明確になると、人生の意思決定が驚くほどスムーズになります。
4. 「断る力」を身につける
この考え方は、ウィリアム・ユーリーの『Noと言える人になるための50の方法』と、グレッグ・マキューンの『エッセンシャル思考』からの抜粋です。
どちらの本も、「断る力」が主体的な人生を生きるための重要なスキルであると説いています。
なぜ「断る力」が必要なのでしょうか?
その理由は明確です。
「ノーと言えない人は、他人の人生を生きることになる」からです。
人は他人のお願いを断れないと、気づかないうちに自分の貴重な時間とエネルギーを消耗してしまいます。
これが、主体的に生きられない最大の要因です。
『エッセンシャル思考』の著者グレッグ・マキューンは、人生を変えるためには、「本当に重要なこと以外はすべて捨てるべきだ」と提唱しています。
彼は、断る力を身につける方法として、次のシンプルなルールを示しています。
- 「もし、それが100%のイエスでなければ、ノーと言う」
- 「沈黙の力を使い、余計な説明はしない」
- 「申し訳なさを感じない」
たとえば、職場で「このプロジェクトを手伝ってほしい」と頼まれたとき、すぐに「はい」と答えるのではなく、「考える時間をください」と言うだけで、冷静な判断ができるようになります。
この「一時停止」のテクニックは、ウィリアム・ユーリーの『Noと言える人になるための50の方法』でも推奨されています。
断る力が主体性につながる理由は、「自分の時間とエネルギーをコントロールできるようになるから」です。
断れない人は、他人の要望に振り回され、自分の目標を後回しにしがちです。
しかし、断れるようになると、「自分が優先すべきものに集中できる」ようになります。
これが、主体的な行動を生み出す理由です。
心理学の観点からは、「行動の選択権が自分にあると感じること」が、主体的な生き方を支えるとされています。
これを支えるのが、先ほどもお伝えした心理学者エドワード・L・デシとリチャード・ライアンが提唱した「自己決定理論(Self-Determination Theory)」です。
自己決定理論では、人間は「自律性」「関係性」「有能感」という3つの基本的な欲求を持つとされています。
断る力を身につけることで、「自律性」が高まり、「自分の人生は自分がコントロールしている」という感覚が得られます。
これにより、主体的な行動が自然に生まれるのです。
最後に、実践的なポイントをまとめます。
- 「考える時間をもらう」…すぐに答えを出さず、1分の猶予を自分に与える。
- 「理由を言わない」…「今回は難しいです」とだけ答え、余計な説明をしない。
- 「ノーは他人の否定ではない」…自分を守るための行動であり、他人を否定する行為ではない。
まとめると、『Noと言える人になるための50の方法』と『エッセンシャル思考』に基づく「断る力」は、主体性を高めるための必須スキルです。
断ることで、あなたの人生の優先順位が明確になり、他人に支配されない主体的な行動が可能になります。
今日から、少しずつ「ノー」と言う練習をしてみてください。
小さな「ノー」から大きな変化が生まれます。
5. 「やりたいことリスト100」を作る
この考え方は、『LIFE SHIFT(ライフシフト)』(著:リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット)や、『夢をかなえるゾウ』(著:水野敬也)からの抜粋です。
どちらの本にも共通するのは、「自分が何をしたいのかを明確にすることが、主体的な人生の第一歩である」という考え方です。
なぜ「やりたいことリスト100」を作ることが主体的な行動につながるのでしょうか?
その理由は、「ゴールを言語化することで、脳のRAS(網様体賦活系)を活性化させるから」です。
RAS(網様体賦活系)とは脳のフィルタリング機能のことで、私たちは普段膨大な情報にさらされていますが、実はRASが「重要だ」と判断した情報だけを認識します。
たとえば、赤い車が欲しいと思った瞬間から、道を歩いていても「赤い車」が目に入るようになるのはこの仕組みのためです。
『LIFE SHIFT』では、100年ライフの時代を生きる上で、「自分の未来を自分で設計する」ことの重要性が説かれています。
長い人生の中で、1つの職業に固執するのではなく、「マルチステージな人生を主体的に生きる」ために、自分が何をやりたいのかを明確にする必要があるとしています。
この明確化の手段として、「やりたいことリスト100」が効果的です。
一方、『夢をかなえるゾウ』では、神様のガネーシャが「夢を叶えたければ、まずは書き出せ」と語ります。
人は「頭の中だけで考えているうちは行動しない」からです。
「書くことで現実になる」のは、心理学でも明らかにされている現象です。
心理学の実験では、「目標を書き出した人は、書かなかった人よりも行動する確率が42%高まる」というデータがあります。
これは、書くことで潜在意識に刺激を与え、脳が「これを達成しなきゃ!」と捉えるからです。
では、「やりたいことリスト100」をどう作ればいいか?
そのポイントは、「大きな夢も小さな願望もすべて含める」ことです。
たとえば、以下のようなリストが考えられます。
- イタリア旅行に行く
- 3ヶ月で5kgのダイエットを達成する
- 副業で月5万円稼ぐ
- 1年に10冊の本を読む
- 家族と毎月1回外食する
重要なのは、「何を書いてもOK」ということです。
「些細なこと」や「すぐに叶わないこと」も全て書き出してください。
これが、「自分の願望を可視化するプロセス」であり、自分が本当に求めているものが見えるようになります。
このリストを作ることで、主体的になれる理由は、「自分の行動がゴールと結びつくから」です。
目標が曖昧なままだと行動は他人の指示に従う形になりますが、リストが明確だと「自分のゴールに向かうための行動を選択する力」が身につきます。
これにより、自分の人生のハンドルを自分で握っている感覚が生まれ、主体的な行動が取れるようになります。
まとめると、『LIFE SHIFT』と『夢をかなえるゾウ』からの考え方を取り入れた「やりたいことリスト100」は、「ゴールを可視化し、RAS(網様体賦活系)を刺激し、主体的な行動を生み出す」ための強力なツールです。
まずは今すぐ、ノートとペンを用意して、思いつく限りの「やりたいこと」を100個書き出してみましょう。
小さな願望もすべて含めてOKです。
これが、あなたの主体的な人生の第一歩になるはずです。
まとめ:主体的に生きるための5つの秘訣
今回紹介した「主体的に生きるための5つの秘訣」をもう一度振り返りましょう。
- 行動の引き金をセットする(出典:『アトミック・ハビット』)
→ すでに習慣化している行動(歯を磨く、コーヒーを飲むなど)を「引き金」にし、新しい行動を結びつけることで、脳の抵抗を減らして主体的な行動が生まれます。 - 小さな行動を続ける(出典:『アトミック・ハビット』、『Tiny Habits(小さな習慣)』)
→ 大きな目標を立てるのではなく、1回の腕立て、1ページの読書のように「小さな行動」を積み重ねましょう。小さな成功体験が自己効力感を高め、主体的な行動が自然と続くようになります。 - 自分の価値観を知る(出典:『7つの習慣』)
→ 自分の価値観を明確にすることで、他人の期待や周囲の目に流されにくくなり、行動の軸ができます。価値観が明確であれば、どんな選択肢も「自分が大切にしたいもの」に基づいて決められるため、人生の主体性が高まります。 - 断る力を身につける(出典:『Noと言える人になるための50の方法』、『エッセンシャル思考』)
→ すべての依頼に「はい」と答えていると、他人の期待に応えるだけの人生になってしまいます。「ノー」と言う力を身につければ、自分が大切にしたいことに集中でき、主体的な行動が取りやすくなります。 - やりたいことリスト100を作る(出典:『LIFE SHIFT』、『夢をかなえるゾウ』)
→ 自分がやりたいことを100個書き出すことで、頭の中の願望が可視化されます。これにより、脳のRAS(網様体賦活系)が活性化し、主体的な行動が生まれます。人は「見える目標」に対して自然と動き出す性質があるのです。
なぜこれらの秘訣が「主体的な行動」につながるのか?
その理由は、「行動のコントロールを自分に取り戻すから」です。
他人の指示や環境に流されているとき、私たちは「自分がやらされている」という感覚を持ちます。
しかし、今回の方法を取り入れれば、「自分が選んでいる」という感覚が得られるようになります。
この「自己決定感」は、心理学における「自己決定理論(SDT:Self-Determination Theory)」でも重要な概念です。
自己決定感が高まれば、人は自分の人生をコントロールしている感覚を持ち、主体的な行動が自然と生まれます。
今日からできる3つの行動
最後に、今すぐできる小さなアクションを3つだけ紹介します。
- 「毎朝のコーヒーの後に、1分だけ読書する」(行動の引き金の活用)
- 「今すぐ、やりたいことを10個だけ書き出す」(やりたいことリストの作成)
- 「今日1回だけ、他人のお願いを断ってみる」(断る力の実践)
この3つの行動のうち、1つだけでも実行すればあなたの人生は少しずつ動き始めます。
大切なのは、「大きな変化ではなく、小さな行動から始める」ことです。
最後にもう一度お伝えしますが、「あなたの人生は、あなたのものであり、あなたがハンドルを握るべきもの」です。
他人の期待や環境に流されるのではなく、自分の価値観を土台にして主体的な行動を選び取っていきましょう。
この5つの秘訣を実践することで、あなたは確実に「自分の人生をものにする力」を手に入れられるはずです。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
ぜひyoutubeのチャンネル登録もお願いします。
目標はチャンネル登録者数1万人です!!
宜しくお願いします!!