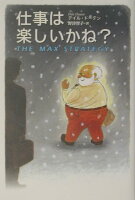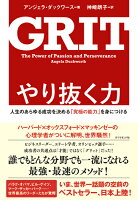Contents
根性ゼロでも続く!やり抜く力を科学するズルい脳習慣
どうも、効率脳研究ラボのSHOです。
「人生の最適化」をテーマに、脳科学や心理学をベースにした“努力に頼らない戦略”を日々研究・発信しています。
最近はYouTubeやブログ、生配信で「どうすれば無理なく続けられるのか?」というテーマを深掘り中。
チャンネル登録者1万人を目指して、現在は1600人。
いや〜、なかなか一筋縄じゃいかないですね(笑)
でも、それもまた“実験”のうち。
失敗すらネタにして、淡々と改善するのがこのラボの流儀です。
さて、今回のテーマは…
「やり抜く力って、結局“根性”なの?」
…この問いにズバッと答えていきます。
というのも、最近SNSや自己啓発系の本で「GRIT(やり抜く力)」ってよく見かけませんか?
でも、正直こう思ったことないですか?
「いや、続けられる人は才能でしょ」
「そもそも、情熱ってそんな簡単に湧いてこないんですけど?」
わかります。
僕も昔そうでした。
でもね、ある研究と1冊の本が、見方を180度変えてくれたんです。
それが、脳科学とあの名著『仕事は楽しいかね?』。
この記事では、「やる気が続かない人」こそ試してほしい、“ズルくて科学的なやり抜き方”を紹介します。
身近な例と実験データをベースに無理せず続けるコツを分かりやすく解説しているので、最後まで読むだけで「よし、自分でもできそうかも」と思えるはずです。
それでは本編、いってみましょう。
やり抜く力は「根性」じゃなく環境が9割
「やり抜く力(GRIT)」って聞くと、“強い意志”“諦めない心”みたいな、気合いと根性のイメージが先にきますよね。
ですが、ある研究では、GRITの正体は“才能”ではなく「情熱 × 粘り強さ」と定義されています。
そして、その2つを生み出すのはほとんどが「本人の性格」ではなく「環境」と「試行錯誤の経験」なんです。
つまり「続けられる人=意志が強い人」ではなく、「続けやすい環境を作るのがうまい人」ということ。
たとえば、僕のYouTube配信。
毎日20時に配信してるんですが、これ、意志力で続けてるわけじゃないんです。
「20時からは配信するもの」と決めたルールと配信を待ってくれてる視聴者の存在が自然と“やらない選択肢”を消してくれている。
だからこそ、意志力を毎日使ってる感じはゼロ。
むしろ「今日は何話そうかな?」とワクワクする余白が残る。
実はこれと同じように「情熱」も「粘り強さ」も“作られる”ものなんです。
米スタンフォード大学の調査で、「粘り強い人」は意志力が強いのではなく“誘惑を回避する仕組み”を上手に設計していることが分かっています。
つまり、やり抜く力に必要なのは「性格」じゃなく、「習慣設計」と「仕組みづくり」。
そしてこの「設計」に欠かせないのが、次のテーマ。
――そう、“実験的な思考”なんです。
『仕事は楽しいかね?』に学ぶ「実験的思考」
「今日の自分は、昨日と同じことをしていないか?」
これは、ある名著の中で語られていた問いです。
その本のタイトルは——『仕事は楽しいかね?』。
ビジネス書というより、人生の“姿勢”を問われるような本なんですが、そこに出てくるキーワードがまさに今回のテーマにドンピシャ。
それが「実験的に生きる」という考え方なんです。
本の中で語られていたのは成功している人は「正解」を探すのではなく「仮説」を持ち、「毎日少しずつ変えてみる」という習慣を持っている、ということ。
これ、めちゃくちゃ本質なんです。
たとえば僕は朝のルーティン。
今でこそ決まったルーティンがありますが、一時期しんどくてもルーティンを決め切っていた時がありました。
そして疲れていたんですね。
というのも、「朝活=これが最強!」みたいな情報に振り回されて、逆に疲れていた時期があったんですよね。
でも、そこである日こう思ったんです。
「これ、全部“実験”にしていいんじゃない?」
・3日間、朝に散歩を取り入れてみたらどうなる?
・早起きより、夜の準備をルール化したら?
・朝イチに脳を使わない作業を入れてみたら?
すると、毎日ちょっとずつ違うから「飽きない」。
しかも、1つうまくいくと「よし、これ採用!」と気持ちよく続けられる。
これがまさに、「GRIT=やり抜く力」を高めるための“仕掛け”なんです。
やり抜く力を持っている人は、「強い人」じゃない。
ただ、毎日を実験の場に変えている人なんです。
この視点を持てるようになると、「続かない」は自然と消えていきます。
なぜなら失敗しても“実験が1つ終わっただけ”なのですから。
「正解」じゃなく「変化」にフォーカスすること。
これが、“ズルいくらい効率的な情熱の育て方”の入り口なんです。
3. 続かない理由は“やり抜く力”じゃなく“楽しさの設計”不足
「自分にはやり抜く力がないんだ…」
そう落ち込んだこと、ありませんか?
僕も昔、何回も思いました。
ダイエットに挫折して、ブログが3日坊主で終わって、「あー自分、やっぱダメだわ」って。
ですが、ある時ふと気づいたんです。
「あれ?“やり抜く力”がないんじゃなくて、単に“楽しくなかった”だけじゃね?」
これ、意外と盲点です。
多くの人が「やり抜けない=自分に問題がある」と思いがち。
でも、実際には――
“楽しさの設計”ができてないだけ。
ここで、脳科学の話を少しだけ。
脳は「快か、不快か」でしか判断していません。
そしてやる気を生むのは、快感物質の「ドーパミン」。
このドーパミン、「今、楽しい」じゃなく「これをやったら良いことがありそう!」っていう“予感”で出るんです。
つまり、行動の中に「報酬の予感」を仕込むことが超重要。
僕はこの仕組みを知ってから、いろんな行動を「小さなご褒美つきの実験」に変えました。
たとえばブログを書く時も、
・書き終えたらお気に入りのウイスキーを一杯飲める
・「今日の実験」として、あえてテンプレを崩してみる
・投稿前に「今日はどこで“ニヤリ”とさせるか?」を自分で楽しみにする
これだけで、「めんどくさい」が「ちょっと面白そう」に変わる。
実は、“やる気”って、自分で設計できるんです。
だから僕は、「続かない」という相談を受けるたびにこう言います。
「それ、あなたがダメなんじゃなくて、脳が退屈してるだけかもよ?」
そしてもう一つ。
「楽しさは、見つけるもんじゃなくて、作るもの」なんです。
この考えが腑に落ちると、やり抜く力ってグッと現実的になります。
次のセクションでは、いよいよ“その仕組み化の全体像”をお見せします。
試行錯誤×やり抜く力=“効率的な情熱”の育て方
ここまで読んでくれたあなたなら、もうお察しかもしれません。
「情熱」や「やり抜く力」って、生まれつきの性格じゃない。
科学的に見れば、それは環境と仕組みによって“後天的に育つスキル”なんです。
ここで、僕が日々使っているシンプルなサイクルを紹介します。
これが、「効率的な情熱」の育て方です。
- ① 仮説を立てる:「これ、もしかして上手くいくかも?」と予想を立てる
- ② 試してみる:小さく行動して反応を見る(←ここが大事)
- ③ 微修正する:「何が良かった?どこで止まった?」をチェック
- ④ 勝ちパターンを定着させる:うまくいった流れをテンプレ化する
この4ステップを回すだけで情熱は“偶然の感情”ではなく“再現可能な戦略”になります。
ポイントは最初から完璧を目指さないこと。
最初の仮説なんてたいてい外れます。
でも、それでいいのです。
「外れる前提で試す」からこそ、修正が冷静にできるし、失敗してもダメージが少ない。
実際、僕もYouTubeで何度も「コケた配信」や「スベったショート動画」を出してきました(笑)
でも、その中で見つけた“ちょっと反応が良かった型”が、今の配信スタイルの土台になってる。
情熱ってね、突然降ってくる閃きじゃなくて、「お、これ上手くいきそう」っていう感覚の積み重ねなんです。
そしてそれは、実験の数に比例して育っていく。
だから、今日から意識してほしいのはこれ。
「これは失敗だった」じゃなく、「実験の結果が出ただけ」
この考え方が根付くと、自分の行動が全て「学び」になる。
そしてその連鎖がやり抜く力を自分の内側に“戦略的にインストール”してくれます。
では最後に、僕自身の実験の記録をちょっとだけ紹介させてください。
実験記録 ― “やる気”より“仕組み”で続けてきた話
ここまで偉そうに語ってきましたが、僕自身、昔はまったく“やり抜ける人間”じゃありませんでした。
22歳で介護の現場に入り、勉強もできず、昇給は年に3000円。
「この人生、詰んだな…」って、マジで思ってたんです。
でも、そこから「脳の使い方」に出会って、少しずつ変わっていきました。
失敗も多かった。
メンターに裏切られて500万の借金を抱えたこともある。
けど、今こうして、YouTubeも、ブログも、ダイエットも、全部“習慣”として継続できているのは、「やる気があるから」じゃありません。
全部、“仕組み”で動かしてるだけ。
たとえば、YouTubeの生配信。
・毎日20時にやると決めて、
・配信部屋に照明とマイクを常設して、
・「よほどのことがない限りやる」という自分ルールを設定。
これだけで、「やるかどうか」を迷う余地がゼロになる。
ダイエットもそう。
16時間断食、一日一食。
最初は「無理じゃない?」って言われましたが
体重が落ちる → 気分が上がる → 続く → 習慣になる
という“報酬のループ”を自分で回しただけ。
ブログも「ネタがないから書けない」じゃなくて、「今日の仮説」をテーマにするだけで、ネタ不足がゼロになった。
全部、“試す → 修正する → 定着させる”の繰り返し。
気合いや意志の強さではなく、ただ、仮説と仕組みで淡々と回してるだけなんです。
だからこそ、声を大にして言いたい。
「やり抜く力は、あなたの中にも絶対にある」
見つからないんじゃない。
まだ、設計されてないだけ。
ラストはその設計の第一歩。
“今日やるべき小さな実験”をご提案して終わります。
まとめ:やり抜く力は、“実験”から
今回のテーマ、「根性ゼロでも続く!やり抜く力を科学するズルい脳習慣」。
ここまで読んでくれたあなたに、伝えたい結論はこれです。
やり抜く力は、「情熱」や「意志」の問題じゃない。
それは環境と仕組み、そして小さな実験の積み重ねで“あとから育てられる力”です。
成功している人が持っているのは生まれ持った才能ではありません。
・日々の選択を仮説として捉え、
・少しずつ変えてみて、
・うまくいった流れを残していく
ただそれだけ。
だから、あなたにもできます。
「情熱がない」「やる気が続かない」と悩んだときは、まずこう問いかけてみてください。
「これは、どう設計したら面白くなるだろう?」
今日から、あなたの人生を“実験の場”に変えていきましょう。
まずは小さな1歩から。
・朝のルーティンを1つだけ変えてみる
・いつもと違う時間に作業してみる
・試した結果を、スマホのメモに残す
この1アクションが、明日のあなたの「情熱のタネ」になります。
そして、もっと効率よく脳を使って人生を最適化したいなら、ぜひSNSでもつながってください。
YouTubeではより深く、具体的な方法を配信中です。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました!
また次回の実験でお会いしましょう。