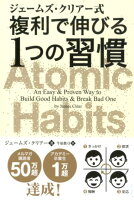Contents
来年こそ自分を変える!脳と体を整えて行動を変える方法
どうも、効率人生研究家のSHOです!
『人生の最適化』をテーマに目標達成や健康的な生活のための情報を日々発信しています。
毎日、YouTubeやInstagram、TikTokで情報を配信中!
さらにブログも毎日更新しています。
現在YouTube登録者1万人を目標に活動中で、今は約1,400人の方に応援いただいています。
引き続きサポートしていただけると嬉しいです!
- 📺 YouTubeチャンネルはこちら
- 📸 Instagram: @sho_mitisirube
- 🎥 TikTok: @sho_mitisirube
今日のブログは年末にふさわしい内容です。
来年こそ自分を変えたいと思っているそこのあなた。
あなたが来年人生を変えるための方法を準備しました。
目標を達成するためには、脳と体を整えることが必須です。
そして、それを実現するためには日常生活の小さな習慣を見直すことが重要です。
変わろうと思っても変われない理由とは?
新しい年を迎えるたびに「今年こそ変わりたい!」と決意する人は多いでしょう。
しかし、現実には「変わりたい」という気持ちだけでは足りず気づけば同じ行動パターンを繰り返してしまいます。
この現象には、心理学や脳科学の観点から明確な理由があります。
1. 目標が大きすぎる
「今年こそダイエットを成功させる」「資格試験に合格する」などの大きな目標を掲げると、達成までの道のりが遠く感じられ、行動を始める前に挫折しがちです。
]心理学者アルバート・バンデューラの「自己効力感理論」によれば目標を細分化して小さな成功体験を積み重ねることで脳内にドーパミンが分泌され、次の行動へのモチベーションが高まります。
2. ネガティビティバイアスの影響
私たちの脳はポジティブな出来事よりもネガティブな情報に敏感に反応する傾向があります。
これは「ネガティビティバイアス」と呼ばれ、失敗や挫折を避けるための進化の名残です。
しかし、このバイアスによって行動を恐れたり自分を過小評価してしまうことがあります。
これを克服するには成功体験を意識的に記録する習慣をつけることが効果的です。
3. 前頭前野のエネルギー消耗
前頭前野は意思決定や計画、衝動抑制などを司る脳の司令塔ですがエネルギー消費が非常に激しい部分でもあります。
一日に多くの決断を求められるとこの部分が疲弊し意志力が低下します。
『スタンフォードの自分を変える教室』(ケリー・マクゴニガル著)では、行動を簡略化し習慣化することで前頭前野への負担を軽減する方法が紹介されています。
4. 環境づくりの甘さ
環境の整備が不十分だと変化を継続するのは難しくなります。
行動科学の研究では行動を始めるハードルを下げる工夫が重要だとされています。
例えば運動を習慣にしたいなら、前夜に運動着を用意しておく。
スマホの利用時間を減らしたいなら、手の届かない場所に置く。
こうした環境の工夫が、行動の実現を大きく助けます。
このように目標の設定方法や脳の仕組みを理解し、現実的な対策を講じることで変わるための一歩を踏み出せます。
次に、その具体的なアクションステップを詳しく見ていきましょう。
目標設定の基本:4つのレベルを考える
目標を立てるのは簡単そうに見えて、実際は難しいものです。
特に「何を目標にするべきか」迷う方は多いでしょう。
目標を立てるときには「抽象度」と「具体性」のバランスを取ることが重要です。
そのために役立つのが、目標を「4つのレベル」に分解して考える方法です。
以下に、それぞれのレベルを解説します。
1. 案件レベル:日々の具体的な目標
案件レベルとは、日常的な仕事やタスクに直結した目標です。
たとえば、以下のようなものが含まれます。
- 毎月の売上目標を達成する。
- 1日3件のクライアント対応を行う。
- 今日中に5ページ分の資料を作成する。
案件レベルの目標は短期的で具体的なものが中心です。
心理学的には、「達成感」を得やすい小さな目標が脳のドーパミン分泌を促し、次の行動へのモチベーションを高めます。
2. 現職レベル:現在の仕事や役割に関連した目標
現職レベルは、今のポジションや職場でどう成長したいかを考える段階です。
具体的には
- 新しいスキルを習得する(例:プログラミングやデザインスキル)。
- チームでのリーダーシップを発揮する。
- 業務効率化の提案を実現する。
このレベルでは、「自己効力感」を意識すると良いでしょう。
自己効力感は「自分は目標を達成できる」と信じる気持ちであり、これを高めることで行動が継続しやすくなるとされています。
3. キャリアレベル:中長期的なキャリアビジョン
キャリアレベルは数年先を見据えた中長期的な目標を設定する段階です。
たとえば
- 3年以内にマネージャーポジションに昇進する。
- 海外でのキャリアを築くために語学スキルを磨く。
- 副業を軌道に乗せて、将来的に独立する。
キャリアレベルの目標は、具体性を持たせつつ、柔軟に変更できるようにすることが大切です。
脳科学的には、「先延ばし癖」を防ぐために、目標を明確な期限や行動計画に結びつけることが推奨されています。
4. ライフレベル:人生全体でどうありたいか
ライフレベルは最も抽象度の高い目標であり、人生全体のビジョンを描く段階です。
以下の質問が参考になります。
- どんな人生を送りたいのか?
- どのような家族関係や人間関係を築きたいのか?
- どのような健康状態を目指すのか?
ライフレベルの目標は、自分の価値観や幸福感に直結します。
心理学ではこれを「エウダイモニア(真の幸福)」と呼びます。
特にポジティブ心理学の分野では、「自分の価値観に基づいた目標設定」が幸福感を大きく高めるとされています。
目標設定の全体像
これらの4つのレベルで考えると目標はある程度見えてくるはずです。
案件レベルから考え、何か腑に落ちない場合は現職レベル、キャリアレベル、ライフレベルとそれぞれのレベルで考えてみましょう。
自分に合ったレベルで目標が明確になります。
この4つのレベルで考えれば、目標が抽象的すぎたり、具体的すぎたりすることを防ぐことが可能となります。
- 案件レベル:毎月の売上目標を達成する。
- 現職レベル:営業スキルを磨き、チームの成績を向上させる。
- キャリアレベル:3年以内に営業部長に昇進する。
- ライフレベル:仕事とプライベートのバランスを取りながら、家族と充実した時間を過ごす。
こうした階層的な目標設定は、心理学的にも行動科学的にも効果的であるとされています。
脳と体を整える3つの基本
1. 食事
「腸は第二の脳」と呼ばれる理由をご存知ですか?
『腸は第二の脳』(藤田紘一郎著)によれば、腸内環境が脳の働きに直接影響を与えることが示されています。
特に注目すべきは、脳内神経伝達物質セロトニンの約90%が腸内で生成されている点です。
脳科学的な観点では腸内環境が悪化すると炎症性物質が増加し、これが脳内でのストレス反応や気分障害を引き起こす可能性があります。
例えば、スタンフォード大学の研究(2019年)では腸内の善玉菌が増加すると、不安やストレスが軽減されることが確認されています。
具体的には、以下の食品を取り入れることが推奨されます。
- 発酵食品:ヨーグルト、納豆、キムチなどが腸内の善玉菌を活性化。
- 食物繊維:野菜、果物、全粒穀物が腸内細菌の栄養源となり、腸内環境を整えます。
- オメガ3脂肪酸:青魚(サバ、イワシなど)やクルミが神経細胞の膜を安定化。
心理学的にもバランスの良い食事が幸福感や集中力の向上に寄与することが確認されています。
例えば、『脳を鍛えるには運動しかない』(ジョン・J・ラテイ著)では、腸内環境を整えることで脳のパフォーマンスが劇的に向上するとされています。
腸内環境を意識した食生活は、脳と体を効率的に整える第一歩です。
日々の選択が、あなたの目標達成力を高める鍵になります。
2. 睡眠
睡眠は脳と体の回復にとって欠かせない要素です。
『スタンフォード式最高の睡眠』(西野精治著)では、「質の高い睡眠」が脳をリセットし、記憶力や判断力を向上させると説明されています。
特に注目すべきは、深い睡眠(ノンレム睡眠)が脳内の老廃物を除去し、神経回路を整える役割を果たしていることです。
脳科学的な研究としてロチェスター大学の論文(2013年)では、睡眠中に脳の「グリンパティックシステム」が活性化し、老廃物を排出することが確認されています。
この過程が不十分だと脳の疲労が溜まり、ストレスや認知機能の低下を招く可能性があります。
効率的な睡眠を確保するための具体策として、以下を試してみてください。
- ブルーライトの遮断:寝る1時間前にスマホやPCをオフにする。
- 一定の睡眠スケジュール:毎日同じ時間に寝起きすることで体内時計を整える。
- 寝室の環境調整:暗く、静かで快適な温度に保つ。
心理学的には睡眠不足が感情制御に悪影響を与えることが知られています。
シカゴ大学の研究(2014年)では、睡眠不足の状態がストレスホルモン「コルチゾール」を増加させ、不安や抑うつ感が高まることが示されています。
睡眠の質を向上させることで脳と体のパフォーマンスを最大化し、日々の目標達成を後押しできます。
生活習慣を見直し、効率的な人生の基盤を作りましょう。
3. 運動
運動は脳と体を効率的に整えるための重要な要素です。
『脳を鍛えるには運動しかない』では、有酸素運動が脳の血流を増加させ、集中力や幸福感を向上させるとされています。
この本では、運動が脳内で分泌される「BDNF(脳由来神経栄養因子)」のレベルを高め、新しい神経回路の形成を促進することが紹介されています。
脳科学的な研究としてハーバード大学の研究(2011年)では、週に3回以上の有酸素運動を行うことで、記憶力が15%以上向上することが確認されています。
また、エンドルフィンやセロトニンといった「幸せホルモン」が分泌されるため、ストレスの軽減にも効果的です。
運動の種類としては、以下がおすすめです。
- ウォーキング:1日20分程度の散歩が脳を活性化。
- ランニング:軽いジョギングは心肺機能を向上させる。
- 筋トレ:適度な負荷をかけることでストレス耐性を向上。
心理学的には、運動が自己効力感(自分はできるという感覚)を高めることも確認されています。
『運動と精神的健康』(ウェンディ・スズキ著)によると日々の運動がポジティブな自己イメージの形成につながり、日常の意欲を高めると述べられています。
「運動を始めるのはハードルが高い」と感じる場合でも、まずはウォーキングや軽いストレッチから始めてみましょう。
小さなステップが脳と体の大きな変化をもたらします。
来年の目標を細分化する
目標を達成するための鍵は、大きな目標を小さく細分化(チャンクダウン)し、すぐに実行できる行動に落とし込むことです。
これは心理学や脳科学の視点からも効果的であるとされています。
小さな成功体験を積み重ねることで自分が達成可能だという感覚(自己効力感)が高まり、さらに行動を継続しやすくなります。
これを脳科学の観点で補足すると脳内の報酬系が活性化し、ドーパミンが分泌されることで行動を繰り返したいというモチベーションが生まれます。
具体例
- 大きな目標:英語を話せるようになる
- 中くらいの目標:毎日単語を30個覚える
- 小さな目標:1日1つの単語を覚える
ハーバード大学の研究(2015年)では目標を具体的かつ小さく設定することで、目標達成率が平均で30%向上することが確認されています。
これは大きな目標をそのままにすると脳がストレスを感じやすいのに対し、小さな目標は脳の負担を軽減するからです。
さらに『小さな習慣』(スティーブン・ガイズ著)では、1日にほんの小さな行動を積み重ねることで目標達成が無理なく続けられるとされています。
1歩ずつ進むことで達成感を感じながら最終目標に近づけるのです。
「今できる小さな1歩」は、最終的に大きな変化を生み出します。
まずは小さな行動を設定して、それを繰り返すことから始めましょう。
まとめ:来年こそ変わるために今できること
来年を最高の年にするためには
- 目標を4つのレベルで考える:案件、現職、キャリア、ライフ。
- 脳と体を整える:食事、睡眠、運動を見直す。
- 小さな行動から始める:目標を細分化して、今できる1歩を踏み出す。
無理をせず自分に合ったペースで取り組むことが、長続きするコツです。
今日のこの流れを実行してみてください。
何も難しいことはありません。
ぜひ、今日から少しずつ始めてみましょう!
いかがでしたでしょうか?
このように、脳科学×行動変容をテーマにしたブログを毎日配信しています!
自分を効率的に変えるためのヒントや方法を発信中です。
さらに詳しい情報や実践的な内容はYouTubeチャンネルでも配信しています。
現在、1万人登録を目指して挑戦中です!
ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。
- 📺 YouTubeチャンネルはこちら
- 📸 Instagram: @sho_mitisirube
- 🎥 TikTok: @sho_mitisirube
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!