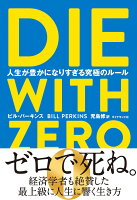Contents
やりたいことを後回しにする人の脳で起きている5つの錯覚
どうも、効率人生研究家のSHOです。
毎日ブログ更新と生配信を続けながら、「脳と行動の設計」で人生を最適化する情報を発信しています。
おかげさまで、YouTubeチャンネル登録者数は1900人を突破しました!
目標は1万人。
これからも、皆さんの「報われる努力」を応援できるよう発信していきます。
今回のテーマは「やりたいことを後回しにする人の脳で起きている5つの錯覚」というテーマでお送りいたします。
・本当はやりたい。でも「なぜか動けない」のは、なぜ?
・「やらなきゃとは思ってる」「でもなぜか腰が重い」──
そんなふうに、自分でも理由がわからないまま行動できずあとでモヤモヤしてしまうことってありませんか?
意志の弱さ?気合いが足りない?
実は、その原因の多くは“脳の錯覚”にあります。
この記事では、次のことがわかります。
- なぜ人は「本当にやりたいこと」を後回しにしてしまうのか
- その裏で脳が勝手にかけている「5つのフィルター」とは?
- 今日から“未来が変わる行動”を起こすシンプルな対処法
あなたの「やりたいのに、できない」を科学的に解決するヒントが、ここにあります。
脳が「やりたいこと」を後回しにする5つの錯覚
行動できないのは意志のせいではありません。
あなたの中で、“見えない誤作動”が起きているのです。
脳には、やる気を妨げる5つの認知バイアスがあります。
これらを理解することで、自分の行動を正しく“設計”できるようになります。
1. 「未来はたっぷりある」という錯覚
「まだ時間がある」と思う心理は、脳の“現在バイアス”によるものです。
人は「今すぐの快楽」に強く反応し、「将来の損失」は軽視する傾向があります。
そのため、本当に大切な目標(英語、資格、旅行など)ほど後回しになりがちです。
『DIE WITH ZERO』という本では「人生には使いどきがある」と語られています。
体力・時間・自由の3つが揃う“今”は、実は非常に貴重な時間なのです。
2. 「やる気が出たらやろう」という錯覚
やる気は「出る」のではなく「動いたあとに湧く」ものです。
脳内でドーパミンが分泌されるのは、「行動した後」が圧倒的に多いという研究があります。
待っていても、気分任せでは始まりません。
だからこそ、「5分だけやってみる」や「形だけ準備しておく」など、“動かされる”のではなく“動き始める”ための仕組みが必要です。
3. 「今これをやっておかないと不安」という錯覚
脳は損失を避けるための行動を優先する性質があります。
たとえば通知チェック、SNS返信、細かいタスクなどは「やらないとマズい」という焦りに駆られて先に手を出してしまいがちです。
しかし、それは未来を変える行動とは限りません。
『1440分の使い方』という本では、「緊急ではないが重要なこと」に最優先で時間を割くべきとされています。
4. 「ちゃんと準備が整ってから」という錯覚
完璧主義は、行動を止めるもっとも強力なブレーキの一つです。
「知識が足りない」「まだ時間がない」と準備にこだわるうちにチャンスそのものが過ぎてしまうこともあります。
“不完全で始めて、途中で修正する”くらいの柔軟性が時間を有効に使う人の共通点なのです。
5. 「今じゃなくても困らない」という錯覚
「あとでも大丈夫」という判断は、未来の自分への丸投げです。
その“あとで”が、いつまでたっても来ないことも少なくありません。
名著『ロングゲーム』では、未来のために今を選ぶ力を「戦略的鈍感力」と呼びます。
目の前の快や雑音に流されず、“自分の人生で重要なものは何か”を毎日確認する視点が必要です。
今すぐできる「行動スイッチ」3つの工夫
「じゃあ、どうすれば後回しをやめられるのか?」
ここでは脳の錯覚を上書きし、“行動が自然に始まる”ための小さな工夫を3つご紹介します。
1. 「1分だけやる」と決める
人の脳は「始めるまで」がもっともエネルギーを消費します。
逆に、1分でも始めてしまえば、意外とそのまま続けられることが多い。
これは「作業興奮」という仕組みによるもので、最初の小さな行動がドーパミンのスイッチを押し、やる気を引き出します。
“完璧”ではなく“開始”を目標にするのが、後回しグセへの第一歩です。
2. 「タイムロック式の予定」を入れる
“いつでもできる”ことは、脳にとって“今じゃなくてもいい”ことに変わってしまいます。
15時から読書、19時からアウトプットなど、
「行動の時間」を先に予約しておくことで、脳の中に「実行前提」のスイッチが入ります。
Googleカレンダーでも、紙の手帳でもOK。
大事なのは「時間を“空けておく”」ことです。
3. 「1アクション目を見える化」する
人は“何をすればいいか”が曖昧なときに、後回しにします。
読書なら「本を机に出す」、運動なら「着替えを出しておく」、ブログなら「タイトルだけ決めておく」など、1歩目をあらかじめ準備しておくだけで、行動のハードルは激減します。
これは環境設計の一部で、NLPや行動科学でも高く評価されている手法です。
まとめ:脳のクセを知れば、行動は変えられる
やりたいことを後回しにしてしまう理由は、あなたの意志の弱さではなく、脳のクセです。
今日ご紹介した錯覚は、誰の中にもある“見えない壁”のようなもの。
- 未来はたっぷりあるという錯覚
- やる気が出たら始めようという錯覚
- 今これをやらないと不安という錯覚
- 完璧に準備してからやるという錯覚
- 今じゃなくても困らないという錯覚
これらを意識するだけでも、行動の優先順位が自然と変わってきます。
あなたの時間は、あなたの命そのものです
今日という1日は、二度と戻ってきません。
大きな一歩じゃなくていい。1分から動いてみる。
それだけでも、未来は変わり始めます。
今回の記事では“なぜ後回しになるか”を解説してきましたが、
実はこの続きとして、「どう行動を逆算設計するか」を、YouTubeのメンバー限定で深堀りしています。
有料記事では、以下のような内容を詳しく解説しています。
- 時間=命という設計視点の具体例
- 人生の優先順位を整理する「3つの質問」
- 朝・昼・夜の逆算ルーティンと行動スイッチ設計
- 自分の1440分を使い切る「時間予算ワーク」
「自分の時間に責任を持ちたい」
そう思った方は、ぜひこちらも読んでみてください👇
▶ 死から逆算する行動設計──命の今日時間を取り戻す“3つの質問”と逆算ルーティン術
▼ SNSでも日々の気づきやルーティンを発信中 ▼
あなたの大切な時間が、「本当に生きる時間」になりますように。