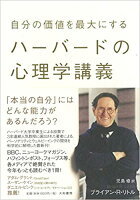Contents
ハーバード式×心理術で自分も他人も動く!行動最適化メソッド
「人は“気合い”では動かない。“仕組み”でしか動かない。」
どうも、効率脳研究ラボのSHOです。
「人生をどうやったら効率よく変えられるか?」をテーマに脳科学と心理学をベースにした実践的な知恵を毎日発信しています。
ありがたいことに、YouTubeチャンネルも少しずつ仲間が増え現在は登録者1600人。
目指すは10,000人。
人生を本気で変えたい人の“脳の使い方”を、誰よりも分かりやすく届ける場所にしたいと思っています。
さて。
今回のテーマは、「自分も他人も思うように動かせるようになる方法」です。
もしあなたが、「何度言っても動いてくれない部下」に悩んでいたり、「やる気が続かない自分」にウンザリしているなら、この先の話は間違いなくあなたの武器になります。
なぜなら、人は“気合い”では動かない。
動かすには、脳のスイッチと心理のトリガーをちゃんと理解する必要があるのです。
今回ご紹介するのは、ハーバードの心理学講義、影響力の武器、そしてコールドリーディングの要素を組み合わせた、効率脳研究ラボオリジナルの「行動ROIマップ」です。
このメソッドを知れば、自分の行動も、人の行動も、無理なく最適化できるようになります。
読み終わるころには、きっとこう思っているはずです。
「あ、自分は変われる。人も動かせる。」
と。
他人を動かす「心理スイッチ」を押せ
「どうしてあの人、動いてくれないんだろう?」
そう思ったことがある方に、まず知っていただきたい前提があります。
人は“やる気”で動くのではなく、“仕組み”で動くものなんです。
その仕組みとして有名なのが、ロバート・チャルディーニが提唱した6つの心理スイッチです。
- 返報性:何かを受け取ると、お返ししたくなる
- 一貫性:一度「はい」と言うと、行動を続けたくなる
- 社会的証明:「みんなやっている」は最大の安心材料
- 好意:好感のある人の言葉には耳を傾けやすい
- 権威:専門家や実績のある人の意見は信頼されやすい
- 希少性:「今だけ」「あなただけ」に人は弱い
これらは、誰にでも働く“人間の習性”です。
つまり、相手が動かないのは「性格のせい」ではなく、「押し方の問題」かもしれません。
ただし、もうひとつ大事な視点があります。
それは、人によって効くスイッチが違うということです。
たとえば、論理的なタイプには「根拠」や「数字」が響きますし、感情型の人には「共感」や「物語」が効果的です。
このように、相手に合わせてスイッチを選ぶ視点が必要になります。
効率脳研究ラボでは、これを「説得=才能ではなく、スキル」と捉えています。
つまり、スイッチの場所さえ分かれば、誰でも人を動かせるということです。
「ちゃんと伝えたのに、なぜ動いてくれないんだろう…」
そう感じたときは、ぜひ一度こう考えてみてください。
“相手の取扱説明書”を読まずに、ボタンを連打していないか?と。
成功する目標は「意味」より「達成できそう」がカギ
「今年こそ本気を出す」
「自分を変えたい」
そう思って立てたはずの目標が、いつの間にか記憶の彼方へ…。
そんな経験、きっと誰にでもあるのではないでしょうか。
その理由は単純で、脳は“達成できる気がしない目標”にワクワクしないからです。
やる気や根性ではなく、脳の設計ミス。
これが継続できない正体です。
効率脳研究ラボでは、目標の価値を次のように定義しています。
目標の価値 = 意味 × 成功確率
「社会の役に立ちたい」「世界を変えたい」
素晴らしい志ですが、成功確率が極端に低いと、脳はその目標を「無理ゲー」と判断し、行動を止めてしまいます。
一方で、「ブログを1本書く」「5分だけ運動する」など、今の自分でも“やれそう”な目標は、脳にとってちょうどいい刺激になります。
行動は、意味の大きさより、成功体験の積み重ねで続いていくのです。
目標が大きすぎて動けないと感じたときは、ぜひ「意味のあることを小さく始める」という考え方を取り入れてみてください。
たとえばこんな感じです。
- 1日1ページだけ本を読む
- 毎朝1行だけ日記を書く
- 気になっている人に「ありがとう」と伝える
これらは一見、小さな行動ですが、脳に「やれた!」という成功体験を届けるには十分です。
この積み重ねが、結果的に自分の未来を変えていきます。
目標は、立てた瞬間がゴールではありません。
脳が「やれそう」と思える設計にすることで、初めて“動く”ようになるのです。
「玉ねぎ型」と「アボカド型」あなたのキャラはどっち?
職場や人間関係の中で、「自分らしくいるのが正しい」と思い込んでいませんか?
もちろん“自分らしさ”は大切です。
でも、そのキャラが今の環境と合っていなければ、苦しさが生まれます。
心理学には「セルフモニタリング」という概念があります。
簡単に言えば、状況に応じて自分のふるまいを調整できる力のことです。
この特性には、大きく分けて2つのタイプがあります。
- 玉ねぎ型:場面ごとにキャラを変えられる柔軟タイプ
- アボカド型:どこにいても一貫して自分らしさを貫くタイプ
どちらが正しい・間違っているという話ではありません。
大事なのは、今のあなたが置かれている環境と“自分のキャラ”が噛み合っているかどうかです。
たとえば、内向的で静かな人が、毎日ノリのいい接客現場に放り込まれたらどうなるか。
最初は頑張れても、だんだんと“演じ疲れ”を起こしてしまいます。
逆に、場の空気を読みながら自分を切り替えられる「玉ねぎ型」の人は、多少しんどくても、その場に合わせたふるまいで乗り切ることができます。
でもここで注意したいのは、玉ねぎ型の人も、ずっと“演じ続ける”と消耗するという点です。
だからこそ、自分のキャラに合った環境を選ぶか、または、演じるキャラと素の自分を切り替えられる“回復の時間”を意識的に持つことが必要なのです。
キャラを脱げる場所が、自分を守るスイッチになる
どんなに器用な人でも、ずっと“キャラを演じ続ける”のはしんどいものです。
外では明るく振る舞っていても、家に帰ってぐったり…なんてこと、ありませんか?
心理学ではこれを「回復の場」と呼びます。
自分を取り繕わずにいられる、安全な時間と空間のことです。
効率脳研究ラボでは、これを少しユーモラスに“キャラを脱げるサウナタイム”と呼んでいます。
サウナに入っているとき、人はだいたい無言です。
肩書きも役割も外れて、ただ「自分」に戻る時間。
あの感覚こそが、現代の思考疲れをリセットする鍵になります。
大事なのは、「自分を演じること」が悪いのではないということ。
むしろ、外でキャラを使いこなせる人ほど、社会の中で強く生きられます。
でも、どこかで必ず“キャラを脱げる場所”を確保しておくこと。
それがなければ、どれだけ前に進んでも、心がすり減ってしまいます。
あなたにとってのサウナは、どこでしょうか?
ひとりカフェ、散歩時間、スマホを見ない10分間でもいいんです。
「ちゃんと休むこと」は、行動力の土台を守る一番の戦略です。
まとめ:スイッチを知れば、人生はもっと動き出す
いかがでしたでしょうか?
今回は、「自分も他人も動かす、心理と行動の最適化」をテーマにお届けしました。
人が動けない理由は、「やる気がないから」ではありません。
脳の性質を知らず、スイッチの場所を間違えているだけなんです。
今日ご紹介した内容は、すべて小さなテクニックのように見えて、実は「人生を動かす土台」になるものばかりです。
- 性格は変えなくていい。行動の幅を知ることが大事。
- 他人を動かすには、“相手の取扱説明書”を読もう。
- 意味よりも、成功しやすい目標を小さく始める。
- キャラは演じてもいい。でも脱げる場所もつくる。
まずは今日、できそうなものをひとつだけ。
「成功しやすい目標をひとつ選んで、小さく動く」
それだけで、脳のエンジンは静かに、でも確実にかかり始めます。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
少しでも「あ、これ使えるかも」と思っていただけたなら嬉しいです。
効率脳研究ラボでは、脳科学と心理学をもとに「行動と人生を変えるヒント」を毎日発信しています。ぜひSNSでもフォローいただけると励みになります!
あなたの「やりたい」が、ちゃんと動き出す毎日になりますように。
これからも応援よろしくお願いいたします。